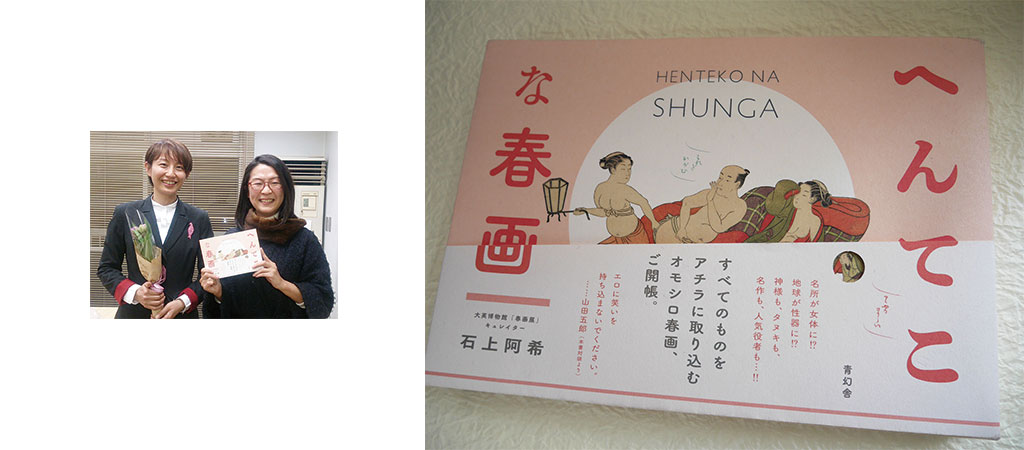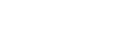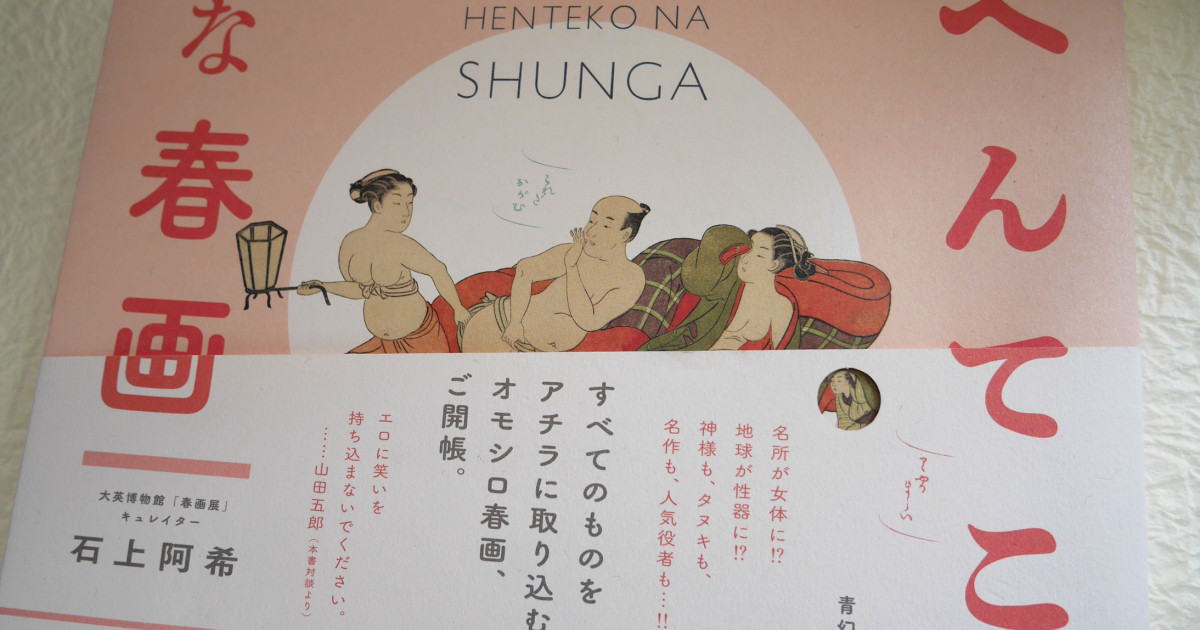京都 細見美術館の「春画展」
2月6日より、京都の細見美術館で行われている「春画展」。
昨秋、東京の永青文庫での開催時
数カ月で10年分の入場があったとか…
性別・年齢などそれぞれに興味の内容は違えど
古来からひとの欲は変わらずといったところでしょうか。
春画の伝統は京都、ということで
京都展だけの展示もあり、
笑いも盛り込まれたユニークな展示内容でした。
特に展示冒頭の
平戸千里ヶ浜温泉 ホテル蘭風所蔵「相愛の図屏風」
かつて平戸のお殿様のものだったという
その大きさの迫力
子細に描かれた着物の柄の美しさは言わずもがな。
対になっている文字の躍動感も素晴らしいものです。
しかし、
局部も同じく大きく子細に描かれており…
これを囲んで宴会していたというから
笑いがこみ上げてきます。
なんと大胆で、ばかばかしいことでしょう。
東京展と同じく、
ひとつひとつをじぃ~っと凝視しているおじいちゃまも居られましたが
昨夏天王寺で行われた肉筆浮世絵展同様、
その時代ならではの耽美な世界にひたることができました。
そうそう、私の感覚がずれているからなのかわかりませんが、
入場者の男女比が話題になることをとても不思議に感じています。
ことさらな讃美も不要ですが、
そんなに貶めたり過敏になることもないと思いますよ。
「女性一人で入場したらどう見られるかが心配で…」という方もおられましたが、
心配しなくても誰もあなたのことなど見ていません。
みんな自分の興味に夢中ですから。
でも、もしも安心材料が必要なら…
美術館の方が仰るには、男女比は半々、
東京よりも京都の方が女性の入場割合が多いそうですよ^^
2日間限定「女性のための春画サロン」
さて、この開催にあわせて
大英博物館の春画展キュレーターを務められた
石上先生を講師として、
「女性のための春画サロン」がひらかれました。
約20名で
「笑い絵としての春画、艶本」と題したお話を聴講。
先生が春画に興味を持ったきっかけや
その当時の風俗文化、
外国人の視点など
日本特有のおおらかで美しい作品が生まれた背景を知りました。
特に「誰が春画をながめるのか?」というお題では、
「艶色水香亭」や「逢夜雁之声」など
知識なしには発見しえない
さまざまな交わりの愉しみが!!
この当時西洋では、
映画「ヒステリア」の時代あたりか~と膝を打ったり、
まさにリバーレース機がイギリスで発明されたその同年!!
など、
自分のフィルターと重ねることで興味が高まり、
理解も深まったような気もしました。
(余談ですが、
今もう一度やってみたらもっと盛り上がりそう!)
大英博物館での会期中、
ワークショップ参加者から挙がった
「逢見八景」で女性器を正面から美しく描くことへの感嘆など、
たくさんの発見がありましたが、
春画を受け止める社会の変容を最も顕著に感じたのが呼称。
偃息図(おそくず)、枕絵、笑い絵、つがい絵、
艶本、絵本、笑本、会本、咲本(えほん)
字面からも
楽し気な様子がうかがえるものが
明治以降
醜画、怪画、淫画と変化しています。
この辺の裸、性への価値観の変化は
フォスコ・マライーニの著書と部分的にリンクするなぁと納得。
そして、100年が巡り
春画展が行われているとは!なんとも興味深いものですね。
「春画サロン」の聴講を終えて
いま、インナーの業界では
昨年あたりからじわじわとイタリアのXo-luxory
フランスのMaison Close
などのプレイフルランジェリーがトレンドです。
伊勢丹新宿店でもピックアップされています。
遊び心のあるエロティックさ、だけどシック
そして、女性自らが選びとるという点は
春画に近いものがあるとも感じます。
それを許容する社会の変化も。
なんでもあけすけや美化することがよいとは言いませんが、
時の流れとともに変わる価値観を楽しみたいもの。
芸術や学術とも異なる、
おおらかな楽しみ方として
石上先生の「へんてこな春画」は読みやすく、
タイトルのとおり笑える要素満載でした。
面白くて、ためになる時間を過ごすことができましたので、
うれしくて書籍とともに記念写真を…
石上先生、本当にありがとうございました。